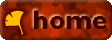カラヤンとの出会い
 「何、カラヤンが来るって、まさか。」
それは、1973年10月31日(水)、学園祭の準備で慌ただしい日であった。黒のタ−トルネックに、ブレザ−という気軽ないでたちで、ついにカラヤンは、私たちの目の前に現れたのである。
ヘルベルト・フォン・カラヤン、彼ほど実力、名声ともに世界に知れ渡っている指揮者はいない。まさに、20世紀が生んだ今世紀最大の指揮者であり、まさに《楽壇の帝王》であった。
彼は、1908年4月5日、オ−ストリアのザルツブルグに生まれた。幼少より、その音楽的才能をあらわし、最初ピアニストとして音楽界にデビュ−した。しかし、ピアノでは自分の目指す音楽が表現できないと悟った彼は指揮者になる決心をしたのである。
オ−ストリア世界屈指のオ−ケストラ、ウィ−ン・フィルハ−モニ−管弦楽団の常任指揮者を歴任し、その後世界最高のオ−ケストラ、ベルリン・フィルハ−モニ−管弦楽団の終身常任指揮者として、1989年、その地位を辞するまで活躍した。その年、7月16日、ザルツブルグ郊外にて死去した。享年81歳であった。
彼は、芸術のため、美の追求のためには、決して妥協しない完全主義者であった。彼の理想とする音楽を奏でるために、世界各地から世界最高の演奏者がベルリン・フィルに集められた。
彼は、最も美しい音楽を聴かせてくれる指揮者であり、彼がクラシック音楽界に残した業績は偉大であった。
そんな人物が、私たちのようなアマチュアのオ−ケストラ(上智大学管弦楽団)の目の前に現れた指揮をしてくれたのであるから、それは私たちにとってだけでなく、日本にとっても一大事であった。カラヤンにしても、アマチュア・オ−ケストラを見ることは最初であったと思う。このニュ−スは、当時、日本で一大センセ−ションを起こし、その日のNHKニュ−スで取り上げられ、翌日の朝も《スタジオ102》で紹介された。
「何、カラヤンが来るって、まさか。」
それは、1973年10月31日(水)、学園祭の準備で慌ただしい日であった。黒のタ−トルネックに、ブレザ−という気軽ないでたちで、ついにカラヤンは、私たちの目の前に現れたのである。
ヘルベルト・フォン・カラヤン、彼ほど実力、名声ともに世界に知れ渡っている指揮者はいない。まさに、20世紀が生んだ今世紀最大の指揮者であり、まさに《楽壇の帝王》であった。
彼は、1908年4月5日、オ−ストリアのザルツブルグに生まれた。幼少より、その音楽的才能をあらわし、最初ピアニストとして音楽界にデビュ−した。しかし、ピアノでは自分の目指す音楽が表現できないと悟った彼は指揮者になる決心をしたのである。
オ−ストリア世界屈指のオ−ケストラ、ウィ−ン・フィルハ−モニ−管弦楽団の常任指揮者を歴任し、その後世界最高のオ−ケストラ、ベルリン・フィルハ−モニ−管弦楽団の終身常任指揮者として、1989年、その地位を辞するまで活躍した。その年、7月16日、ザルツブルグ郊外にて死去した。享年81歳であった。
彼は、芸術のため、美の追求のためには、決して妥協しない完全主義者であった。彼の理想とする音楽を奏でるために、世界各地から世界最高の演奏者がベルリン・フィルに集められた。
彼は、最も美しい音楽を聴かせてくれる指揮者であり、彼がクラシック音楽界に残した業績は偉大であった。
そんな人物が、私たちのようなアマチュアのオ−ケストラ(上智大学管弦楽団)の目の前に現れた指揮をしてくれたのであるから、それは私たちにとってだけでなく、日本にとっても一大事であった。カラヤンにしても、アマチュア・オ−ケストラを見ることは最初であったと思う。このニュ−スは、当時、日本で一大センセ−ションを起こし、その日のNHKニュ−スで取り上げられ、翌日の朝も《スタジオ102》で紹介された。
 そもそも、カラヤンを私たちの前に呼び寄せたのは、我がオケの女性チェリストである。
その時、カラヤンは、NHKの招待により、手兵ベルリン・フィルを率いて6度目の日本公演のため来日していた。カラヤンの異常なほどの人気のため、数10回の公演のチケットを手に入れるためには、まず抽選に当選しなければならないほどであった。
ベルリン・フィルのチェリストと知り合いになり練習場に行った彼女は、廊下で練習を終えたカラヤンの姿を目にとめ、我を忘れてカラヤンの側に駆け寄り話しかけた。大学でドイツ語を学んでいる彼女は必死であった。当然、彼女は警備人に追い返されそうになったが、カラヤンは、彼女の名前を控えておくようマネ−ジャ−に命じ、その場を去った。そして、彼女はカラヤンに来てもらおうという、とんでもない考えを思いついたのである。大学に戻るやいなや私たち部員より署名を集めはじめた。みんな冗談めいた気持ちで署名したようであるが、部員全員より署名を集めた。
その日の夜の演奏会に行った彼女は、願いを花束の中に託した。翌日、彼女は再び練習場を訪れた。今回はマネ−ジャ−を通して正式にカラヤンと会うことができた。彼女の必死の願いにカラヤンは承諾した。すっかり彼女はカラヤンに気に入られてしまった。
10月31日、午前11時、彼女は、練習場へカラヤンを迎えに行った。カラヤンをソフィア・フィル(上智大学管弦楽団)にお迎えに来ましたという言葉にベルリン・フィルの団員たちは、「マエストロが!信じられない!今までだって一度だってこんな事はなかった。」と口々に驚きの声を挙げたと言う。カラヤンの特別控室に案内された彼女は、「あなたをお迎えにあがりした。」と挨拶すると、カラヤンは笑顔で、「何を演奏しますか?」と尋ねたという。その時、私たちが練習していたのは、ベ−ト−ベンの第9交響曲「合唱」と序曲「エグモント」であった。
12時をまわる頃、カラヤンは、にこやかに車に乗り込み私たちの待つ上智大学のある四ツ谷に向かった。
一方、カラヤンが来るのを朝から待っている私たち部員約80名は、まだ半信半疑である。「本当に来るのかなぁ」みんな、そんな気持ちであった。カラヤンの気を悪くすることのないように私たちは、演奏会用の黒の上下のス−ツに着替えていた。また、カラヤンに万一の事があってはならないという配慮から、大学内外は、物々しい警備体制が秘密裏にひかれた。
そもそも、カラヤンを私たちの前に呼び寄せたのは、我がオケの女性チェリストである。
その時、カラヤンは、NHKの招待により、手兵ベルリン・フィルを率いて6度目の日本公演のため来日していた。カラヤンの異常なほどの人気のため、数10回の公演のチケットを手に入れるためには、まず抽選に当選しなければならないほどであった。
ベルリン・フィルのチェリストと知り合いになり練習場に行った彼女は、廊下で練習を終えたカラヤンの姿を目にとめ、我を忘れてカラヤンの側に駆け寄り話しかけた。大学でドイツ語を学んでいる彼女は必死であった。当然、彼女は警備人に追い返されそうになったが、カラヤンは、彼女の名前を控えておくようマネ−ジャ−に命じ、その場を去った。そして、彼女はカラヤンに来てもらおうという、とんでもない考えを思いついたのである。大学に戻るやいなや私たち部員より署名を集めはじめた。みんな冗談めいた気持ちで署名したようであるが、部員全員より署名を集めた。
その日の夜の演奏会に行った彼女は、願いを花束の中に託した。翌日、彼女は再び練習場を訪れた。今回はマネ−ジャ−を通して正式にカラヤンと会うことができた。彼女の必死の願いにカラヤンは承諾した。すっかり彼女はカラヤンに気に入られてしまった。
10月31日、午前11時、彼女は、練習場へカラヤンを迎えに行った。カラヤンをソフィア・フィル(上智大学管弦楽団)にお迎えに来ましたという言葉にベルリン・フィルの団員たちは、「マエストロが!信じられない!今までだって一度だってこんな事はなかった。」と口々に驚きの声を挙げたと言う。カラヤンの特別控室に案内された彼女は、「あなたをお迎えにあがりした。」と挨拶すると、カラヤンは笑顔で、「何を演奏しますか?」と尋ねたという。その時、私たちが練習していたのは、ベ−ト−ベンの第9交響曲「合唱」と序曲「エグモント」であった。
12時をまわる頃、カラヤンは、にこやかに車に乗り込み私たちの待つ上智大学のある四ツ谷に向かった。
一方、カラヤンが来るのを朝から待っている私たち部員約80名は、まだ半信半疑である。「本当に来るのかなぁ」みんな、そんな気持ちであった。カラヤンの気を悪くすることのないように私たちは、演奏会用の黒の上下のス−ツに着替えていた。また、カラヤンに万一の事があってはならないという配慮から、大学内外は、物々しい警備体制が秘密裏にひかれた。
カラヤンが来るのに先立って、NHKの放送器具が会場に運び込まれた。練習をしているうちにカラヤンの到着予定時刻は過ぎた。「やはり来るわけないよ。」
しかし、外が少しざわめき始めた。入口の扉が開いた。一斉に立ち上がった。そこにはあのカラヤンが立っていた。スポットライトを浴びた笑顔のカラヤンがそこに立っていた。心から感謝の拍手をカラヤンに送る。
カラヤンについて、人々は、神様だとか、気難しがり屋だとか言う、しかしカラヤンは、やはり人間であり、その笑顔の中の目はとりわけブル−であった。背は思った程、高くはなかった。私たちのオケの常任指揮者(汐沢安彦氏)とコンサ−ト・マスタ−と握手をかわしたカラヤンは、さっそく指揮者に練習を再開させた。曲は、今度演奏会で演奏することになっているベートーベンの第9交響曲、第1楽章であった。カラヤンは、腕を組み、真剣な表情で私たちの回りを歩きはじめた。笑顔は消えていた。カラヤンがそこにいるという緊張感で心臓が張り裂けそうであった。みんな無我夢中であった。
5分位したところで、突然、カラヤンはストップを命じた。そして、つい指揮台に足をかけた。そして、第3楽章を指定した。1楽章を一生懸命練習していた私たちに緊張がみなぎった。カラヤンは、指揮棒なしで、右手を腰にあて、左手だけの指揮であった。奇跡である。カラヤンの指揮で奏でるソフィア・フィルから出てくる音は、聞いたことのない信じられない音であった。カラヤンの指揮のもと、心が一つになったのである。各々が持ちうる音楽的才能を最大限引き出されているのである。まさにカラヤン・マジックである。要所要所で演奏を止めて、慣れない英語で必要な説明をする。カラヤンの声は、美しい音楽とは裏腹に壊れた蓄音機から出てくるようなガ−ガ−声であった。
カラヤンの指揮に、次第に熱がこもってくる。さかんに心のこもった音楽を要求する。カメラの音さえも止めさせた。
時間の経つのも忘れ、カラヤンが練習を終えた時、1時間余りが経過していた。
音楽を奏でる者、音楽を愛する者にとって、カラヤンに目の前で会えただけでなく、指揮をしてもらうという光栄を得た私たちソフィア・フィルのメンバ−の幸福感は口ではとても言い表せない。しかし、カラヤンとの出会いは、これで終わりではなかった。これから私たちに起こる出来事の始まりであった。
 練習を終えたカラヤンは、私たちの演奏に大変満足してくれた様子であった。カラヤンに笑顔が戻った。英語とドイツ語の混じった話をしてカラヤンは去って行った。盛大な拍手で見送ったものの、カラヤンは私たちの無反応を不思議の思ったに違いない。カラヤンの話は次のようであった。
「素晴らしいオ−ケストラです。私は大変満足した。来年ベルリンで開かれる第3回国際青少年音楽コンクールに貴方たちを招待できるよう政府に働きかけましょう。」
カラヤンが帰ったあと、これを知った私たちは飛び上がらんばかりに喜んだのは当たり前である。この時、4年生の中には心密かに留年を決意したものもいた。
練習を終えたカラヤンは、私たちの演奏に大変満足してくれた様子であった。カラヤンに笑顔が戻った。英語とドイツ語の混じった話をしてカラヤンは去って行った。盛大な拍手で見送ったものの、カラヤンは私たちの無反応を不思議の思ったに違いない。カラヤンの話は次のようであった。
「素晴らしいオ−ケストラです。私は大変満足した。来年ベルリンで開かれる第3回国際青少年音楽コンクールに貴方たちを招待できるよう政府に働きかけましょう。」
カラヤンが帰ったあと、これを知った私たちは飛び上がらんばかりに喜んだのは当たり前である。この時、4年生の中には心密かに留年を決意したものもいた。
その日は、カラヤンとの出会いの興奮さめやらず夜遅くまで大学近くの喫茶店で語り合った。
私は、この日より、カラヤンを最も尊敬する人物と決めてしまった。
外国へ行くということ、上智大学管弦楽団の演奏旅行として。しかし、現実は甘いものではなかった。あの日を境として、私たちの真の苦しみ、悩みが始まったのである。
クラブ内で外国行きに関する部会が開かれた。私は、素直な気持ちで外国に行きたい旨を述べた。投票の結果、20数名の反対はあったものの大多数の賛成によって外国行きが決定された。ここにドイツ演奏旅行の準備が始まった。予定されていた国内演奏旅行は全て取りやめとなった。事務的機関として、ベルリン委員会なるものが結成され、旅行手続きの準備、企業、本校卒業生への寄附金活動が開始された。
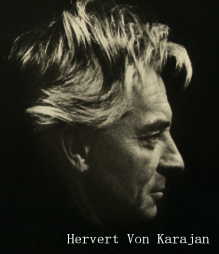 年も明けた1974年1月14日(月)第17回定期演奏会を迎えた。カラヤンが振ったオケということで聴衆の入りはすごかった。上野の東京文化会館大ホールは立ち見客が出るほどであった。ベートーベン序曲《エグモント》、交響曲第9番《合唱》。大成功であった。さっそく、その演奏会のテープをカラヤンに送った。カラヤンからは称賛の手紙が送られてきた。
定演も終わり、いよいよ、ベルリン行きの本格的な練習が始まった。曲は、ウエ−バ−歌劇「魔弾の射手」序曲(コンク−ル課題曲)、武満徹「弦楽のためのレクイエム」、ブラ−ムス交響曲第4番である。
春休み、みなアルバイトに燃えていた。3月下旬、千葉県岩井にて1週間の合宿。しかし練習は思うようにはかどらない。数人の4年生が卒業したために演奏レベルが低下してしまったのである。
4月に入り、40人余りの新入生が入部してきたが、例外を除いてはドイツ公演には連れていけないことになっていた。4月下旬、正式な招待状が送られてきた。
新たな障害である。予想以上に自己負担がかかりそうである。ドイツ滞在費はカラヤン財団持ちであるが、旅費は全額自己負担であるということが明らかになった。約20万円、当時としては大金である。経済的困難な人のために銀行ロ−ンの制度が取り入れられた。ベルリンでのコンク−ルの日程も決まり、それに先立つボンでの演奏会も決定した。
6月に入り、例年通り、東京での定期演奏会が開かれた。この演奏会は、ドイツでの成果を占うものであったが大失敗であった。技術的にも精神的にも未熟で表面的でしかない演奏であった。外部から、しきりに批判の声が聞こえた。「あれで、ドイツだって。」
ドイツ演奏旅行であって、ドイツ観光旅行ではない。ドイツは、バッハ、ベ−ト−ベン、ブラ−ムス等多くの作曲を生み出している音楽の都である。ドイツの人々は音楽を通して、私たちを見るのであり、私たちは日本の代表なのである。
東京での定演の反省として、東京芸大を始め他大学より10名程の優秀な演奏者の補充が決まった。練習もこれまでとは違った気迫と緊張感がみなぎりはじめた。演奏が向上すれば、合奏する歓びも増すものである。充実感を感じながら、演奏は加速度的に高まっていった。
ドイツ出発1週間前、総仕上げの合宿が私の地元、群馬県の富岡市の貫前神社近くの社会教育館で行われた。神社で手を合わせる皆の気持ちは同じであった。
「ドイツ公演が、うまくいきますように。」 (Sophia Philharmony:Horn mkudos910@yahoo.co.jp 改訂98/12/10)
東京新聞記事より
朝日新聞記事より
ドイツ演奏旅行
(参考文献)
チャンスをつかむためには積極的な行動を
(江川ひろし「3分間の名スピーチ」より)
昭和48年の秋のこと、日本にヘルベルト.フォン.カラヤンさんが来日したとき、すばらしい逸話が生まれました。それはカラヤンさんが学生のアマチュア楽団のために、みずから指揮棒を振ったという話です。
カラヤンさんは世界第一級の指揮者です。また、この天才音楽家は気むずかしいことで知られており、関係者は大変な神経の使い方だという報道も新聞をにぎわしていました。
ところでここに、新聞には報道されずNHKのテレビだけに流されたひとつのニュースがありました。それが冒頭に述べた素人管弦楽団の指揮という美談です。
それには次のようなひとりの女子学生の積極的な行動がありました。彼女はテレビに映るカラヤンの表情を見て、なんと人間的深味をたたえた顔だろう、この人はきっと心のやさしい人にちがいない。私たち素人の管弦楽団を指揮してくださらないものだろうか、お願いしてみよう、と思いたったのです。そしてドイツにはよい果物が少ないそうだからと蜜柑を一籠もって訪ねました。
はじめに、マネージャーと面会して手順を考えていました。するとなんと思いがけなく廊下の向こうからカラヤンさん、その人がくるではありませんか。彼女は思い切って積極的に声をかけ、あいさつしました。
「日本ではあなたのことを神さまのように思っています。とても私たちアマチュア楽団などの指揮なんかしていただけないと思いますが、もしその夢がかなえられるなら、と思ってお願いにまいりました。」
彼女はドイツ語を習っていたので、これだけの言葉を一生懸命覚えて行ったのだそうです。そして・・。
テレビのニュースは、学生たちの楽団を前に、あの瞑想スタイルで、しなやかに指揮をする神秘的なカラヤンの姿を映しました。
カラヤンさんは、「私は神さまなんかじゃありませんよ。若い人のアマチュア楽団の指揮をしないなんてことはありません」とやさしく語ったということです。
気むずかしくて有名な世界最高峰の指揮者と素人楽団のとり合わせ、この奇跡のような出来事をあなたはどう思いますか。
話を交わすことで、人と人とのむすびつきができるのです。言葉を交わすことで人間関係が生まれるのです。もし彼女がカラヤンさんと廊下で会ったときに、「あとにしよう」と声をかけなかったら、このすばらしいエピソードは生まれなかったでしょう。
人との出会いを大切に。そしてチャンスを逃がさずに。チャンスの神さまが通ったら、積極的に声をかけて、勇気を持って前髪をつかみましょう。チャンスの神さまは後ろが禿げています。
年も明けた1974年1月14日(月)第17回定期演奏会を迎えた。カラヤンが振ったオケということで聴衆の入りはすごかった。上野の東京文化会館大ホールは立ち見客が出るほどであった。ベートーベン序曲《エグモント》、交響曲第9番《合唱》。大成功であった。さっそく、その演奏会のテープをカラヤンに送った。カラヤンからは称賛の手紙が送られてきた。
定演も終わり、いよいよ、ベルリン行きの本格的な練習が始まった。曲は、ウエ−バ−歌劇「魔弾の射手」序曲(コンク−ル課題曲)、武満徹「弦楽のためのレクイエム」、ブラ−ムス交響曲第4番である。
春休み、みなアルバイトに燃えていた。3月下旬、千葉県岩井にて1週間の合宿。しかし練習は思うようにはかどらない。数人の4年生が卒業したために演奏レベルが低下してしまったのである。
4月に入り、40人余りの新入生が入部してきたが、例外を除いてはドイツ公演には連れていけないことになっていた。4月下旬、正式な招待状が送られてきた。
新たな障害である。予想以上に自己負担がかかりそうである。ドイツ滞在費はカラヤン財団持ちであるが、旅費は全額自己負担であるということが明らかになった。約20万円、当時としては大金である。経済的困難な人のために銀行ロ−ンの制度が取り入れられた。ベルリンでのコンク−ルの日程も決まり、それに先立つボンでの演奏会も決定した。
6月に入り、例年通り、東京での定期演奏会が開かれた。この演奏会は、ドイツでの成果を占うものであったが大失敗であった。技術的にも精神的にも未熟で表面的でしかない演奏であった。外部から、しきりに批判の声が聞こえた。「あれで、ドイツだって。」
ドイツ演奏旅行であって、ドイツ観光旅行ではない。ドイツは、バッハ、ベ−ト−ベン、ブラ−ムス等多くの作曲を生み出している音楽の都である。ドイツの人々は音楽を通して、私たちを見るのであり、私たちは日本の代表なのである。
東京での定演の反省として、東京芸大を始め他大学より10名程の優秀な演奏者の補充が決まった。練習もこれまでとは違った気迫と緊張感がみなぎりはじめた。演奏が向上すれば、合奏する歓びも増すものである。充実感を感じながら、演奏は加速度的に高まっていった。
ドイツ出発1週間前、総仕上げの合宿が私の地元、群馬県の富岡市の貫前神社近くの社会教育館で行われた。神社で手を合わせる皆の気持ちは同じであった。
「ドイツ公演が、うまくいきますように。」 (Sophia Philharmony:Horn mkudos910@yahoo.co.jp 改訂98/12/10)
東京新聞記事より
朝日新聞記事より
ドイツ演奏旅行
(参考文献)
チャンスをつかむためには積極的な行動を
(江川ひろし「3分間の名スピーチ」より)
昭和48年の秋のこと、日本にヘルベルト.フォン.カラヤンさんが来日したとき、すばらしい逸話が生まれました。それはカラヤンさんが学生のアマチュア楽団のために、みずから指揮棒を振ったという話です。
カラヤンさんは世界第一級の指揮者です。また、この天才音楽家は気むずかしいことで知られており、関係者は大変な神経の使い方だという報道も新聞をにぎわしていました。
ところでここに、新聞には報道されずNHKのテレビだけに流されたひとつのニュースがありました。それが冒頭に述べた素人管弦楽団の指揮という美談です。
それには次のようなひとりの女子学生の積極的な行動がありました。彼女はテレビに映るカラヤンの表情を見て、なんと人間的深味をたたえた顔だろう、この人はきっと心のやさしい人にちがいない。私たち素人の管弦楽団を指揮してくださらないものだろうか、お願いしてみよう、と思いたったのです。そしてドイツにはよい果物が少ないそうだからと蜜柑を一籠もって訪ねました。
はじめに、マネージャーと面会して手順を考えていました。するとなんと思いがけなく廊下の向こうからカラヤンさん、その人がくるではありませんか。彼女は思い切って積極的に声をかけ、あいさつしました。
「日本ではあなたのことを神さまのように思っています。とても私たちアマチュア楽団などの指揮なんかしていただけないと思いますが、もしその夢がかなえられるなら、と思ってお願いにまいりました。」
彼女はドイツ語を習っていたので、これだけの言葉を一生懸命覚えて行ったのだそうです。そして・・。
テレビのニュースは、学生たちの楽団を前に、あの瞑想スタイルで、しなやかに指揮をする神秘的なカラヤンの姿を映しました。
カラヤンさんは、「私は神さまなんかじゃありませんよ。若い人のアマチュア楽団の指揮をしないなんてことはありません」とやさしく語ったということです。
気むずかしくて有名な世界最高峰の指揮者と素人楽団のとり合わせ、この奇跡のような出来事をあなたはどう思いますか。
話を交わすことで、人と人とのむすびつきができるのです。言葉を交わすことで人間関係が生まれるのです。もし彼女がカラヤンさんと廊下で会ったときに、「あとにしよう」と声をかけなかったら、このすばらしいエピソードは生まれなかったでしょう。
人との出会いを大切に。そしてチャンスを逃がさずに。チャンスの神さまが通ったら、積極的に声をかけて、勇気を持って前髪をつかみましょう。チャンスの神さまは後ろが禿げています。
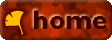

 練習を終えたカラヤンは、私たちの演奏に大変満足してくれた様子であった。カラヤンに笑顔が戻った。英語とドイツ語の混じった話をしてカラヤンは去って行った。盛大な拍手で見送ったものの、カラヤンは私たちの無反応を不思議の思ったに違いない。カラヤンの話は次のようであった。
「素晴らしいオ−ケストラです。私は大変満足した。来年ベルリンで開かれる第3回国際青少年音楽コンクールに貴方たちを招待できるよう政府に働きかけましょう。」
カラヤンが帰ったあと、これを知った私たちは飛び上がらんばかりに喜んだのは当たり前である。この時、4年生の中には心密かに留年を決意したものもいた。
練習を終えたカラヤンは、私たちの演奏に大変満足してくれた様子であった。カラヤンに笑顔が戻った。英語とドイツ語の混じった話をしてカラヤンは去って行った。盛大な拍手で見送ったものの、カラヤンは私たちの無反応を不思議の思ったに違いない。カラヤンの話は次のようであった。
「素晴らしいオ−ケストラです。私は大変満足した。来年ベルリンで開かれる第3回国際青少年音楽コンクールに貴方たちを招待できるよう政府に働きかけましょう。」
カラヤンが帰ったあと、これを知った私たちは飛び上がらんばかりに喜んだのは当たり前である。この時、4年生の中には心密かに留年を決意したものもいた。 「何、カラヤンが来るって、まさか。」
それは、1973年10月31日(水)、学園祭の準備で慌ただしい日であった。黒のタ−トルネックに、ブレザ−という気軽ないでたちで、ついにカラヤンは、私たちの目の前に現れたのである。
ヘルベルト・フォン・カラヤン、彼ほど実力、名声ともに世界に知れ渡っている指揮者はいない。まさに、20世紀が生んだ今世紀最大の指揮者であり、まさに《楽壇の帝王》であった。
彼は、1908年4月5日、オ−ストリアのザルツブルグに生まれた。幼少より、その音楽的才能をあらわし、最初ピアニストとして音楽界にデビュ−した。しかし、ピアノでは自分の目指す音楽が表現できないと悟った彼は指揮者になる決心をしたのである。
オ−ストリア世界屈指のオ−ケストラ、ウィ−ン・フィルハ−モニ−管弦楽団の常任指揮者を歴任し、その後世界最高のオ−ケストラ、ベルリン・フィルハ−モニ−管弦楽団の終身常任指揮者として、1989年、その地位を辞するまで活躍した。その年、7月16日、ザルツブルグ郊外にて死去した。享年81歳であった。
彼は、芸術のため、美の追求のためには、決して妥協しない完全主義者であった。彼の理想とする音楽を奏でるために、世界各地から世界最高の演奏者がベルリン・フィルに集められた。
彼は、最も美しい音楽を聴かせてくれる指揮者であり、彼がクラシック音楽界に残した業績は偉大であった。
そんな人物が、私たちのようなアマチュアのオ−ケストラ(上智大学管弦楽団)の目の前に現れた指揮をしてくれたのであるから、それは私たちにとってだけでなく、日本にとっても一大事であった。カラヤンにしても、アマチュア・オ−ケストラを見ることは最初であったと思う。このニュ−スは、当時、日本で一大センセ−ションを起こし、その日のNHKニュ−スで取り上げられ、翌日の朝も《スタジオ102》で紹介された。
「何、カラヤンが来るって、まさか。」
それは、1973年10月31日(水)、学園祭の準備で慌ただしい日であった。黒のタ−トルネックに、ブレザ−という気軽ないでたちで、ついにカラヤンは、私たちの目の前に現れたのである。
ヘルベルト・フォン・カラヤン、彼ほど実力、名声ともに世界に知れ渡っている指揮者はいない。まさに、20世紀が生んだ今世紀最大の指揮者であり、まさに《楽壇の帝王》であった。
彼は、1908年4月5日、オ−ストリアのザルツブルグに生まれた。幼少より、その音楽的才能をあらわし、最初ピアニストとして音楽界にデビュ−した。しかし、ピアノでは自分の目指す音楽が表現できないと悟った彼は指揮者になる決心をしたのである。
オ−ストリア世界屈指のオ−ケストラ、ウィ−ン・フィルハ−モニ−管弦楽団の常任指揮者を歴任し、その後世界最高のオ−ケストラ、ベルリン・フィルハ−モニ−管弦楽団の終身常任指揮者として、1989年、その地位を辞するまで活躍した。その年、7月16日、ザルツブルグ郊外にて死去した。享年81歳であった。
彼は、芸術のため、美の追求のためには、決して妥協しない完全主義者であった。彼の理想とする音楽を奏でるために、世界各地から世界最高の演奏者がベルリン・フィルに集められた。
彼は、最も美しい音楽を聴かせてくれる指揮者であり、彼がクラシック音楽界に残した業績は偉大であった。
そんな人物が、私たちのようなアマチュアのオ−ケストラ(上智大学管弦楽団)の目の前に現れた指揮をしてくれたのであるから、それは私たちにとってだけでなく、日本にとっても一大事であった。カラヤンにしても、アマチュア・オ−ケストラを見ることは最初であったと思う。このニュ−スは、当時、日本で一大センセ−ションを起こし、その日のNHKニュ−スで取り上げられ、翌日の朝も《スタジオ102》で紹介された。
 そもそも、カラヤンを私たちの前に呼び寄せたのは、我がオケの女性チェリストである。
その時、カラヤンは、NHKの招待により、手兵ベルリン・フィルを率いて6度目の日本公演のため来日していた。カラヤンの異常なほどの人気のため、数10回の公演のチケットを手に入れるためには、まず抽選に当選しなければならないほどであった。
ベルリン・フィルのチェリストと知り合いになり練習場に行った彼女は、廊下で練習を終えたカラヤンの姿を目にとめ、我を忘れてカラヤンの側に駆け寄り話しかけた。大学でドイツ語を学んでいる彼女は必死であった。当然、彼女は警備人に追い返されそうになったが、カラヤンは、彼女の名前を控えておくようマネ−ジャ−に命じ、その場を去った。そして、彼女はカラヤンに来てもらおうという、とんでもない考えを思いついたのである。大学に戻るやいなや私たち部員より署名を集めはじめた。みんな冗談めいた気持ちで署名したようであるが、部員全員より署名を集めた。
その日の夜の演奏会に行った彼女は、願いを花束の中に託した。翌日、彼女は再び練習場を訪れた。今回はマネ−ジャ−を通して正式にカラヤンと会うことができた。彼女の必死の願いにカラヤンは承諾した。すっかり彼女はカラヤンに気に入られてしまった。
10月31日、午前11時、彼女は、練習場へカラヤンを迎えに行った。カラヤンをソフィア・フィル(上智大学管弦楽団)にお迎えに来ましたという言葉にベルリン・フィルの団員たちは、「マエストロが!信じられない!今までだって一度だってこんな事はなかった。」と口々に驚きの声を挙げたと言う。カラヤンの特別控室に案内された彼女は、「あなたをお迎えにあがりした。」と挨拶すると、カラヤンは笑顔で、「何を演奏しますか?」と尋ねたという。その時、私たちが練習していたのは、ベ−ト−ベンの第9交響曲「合唱」と序曲「エグモント」であった。
12時をまわる頃、カラヤンは、にこやかに車に乗り込み私たちの待つ上智大学のある四ツ谷に向かった。
一方、カラヤンが来るのを朝から待っている私たち部員約80名は、まだ半信半疑である。「本当に来るのかなぁ」みんな、そんな気持ちであった。カラヤンの気を悪くすることのないように私たちは、演奏会用の黒の上下のス−ツに着替えていた。また、カラヤンに万一の事があってはならないという配慮から、大学内外は、物々しい警備体制が秘密裏にひかれた。
そもそも、カラヤンを私たちの前に呼び寄せたのは、我がオケの女性チェリストである。
その時、カラヤンは、NHKの招待により、手兵ベルリン・フィルを率いて6度目の日本公演のため来日していた。カラヤンの異常なほどの人気のため、数10回の公演のチケットを手に入れるためには、まず抽選に当選しなければならないほどであった。
ベルリン・フィルのチェリストと知り合いになり練習場に行った彼女は、廊下で練習を終えたカラヤンの姿を目にとめ、我を忘れてカラヤンの側に駆け寄り話しかけた。大学でドイツ語を学んでいる彼女は必死であった。当然、彼女は警備人に追い返されそうになったが、カラヤンは、彼女の名前を控えておくようマネ−ジャ−に命じ、その場を去った。そして、彼女はカラヤンに来てもらおうという、とんでもない考えを思いついたのである。大学に戻るやいなや私たち部員より署名を集めはじめた。みんな冗談めいた気持ちで署名したようであるが、部員全員より署名を集めた。
その日の夜の演奏会に行った彼女は、願いを花束の中に託した。翌日、彼女は再び練習場を訪れた。今回はマネ−ジャ−を通して正式にカラヤンと会うことができた。彼女の必死の願いにカラヤンは承諾した。すっかり彼女はカラヤンに気に入られてしまった。
10月31日、午前11時、彼女は、練習場へカラヤンを迎えに行った。カラヤンをソフィア・フィル(上智大学管弦楽団)にお迎えに来ましたという言葉にベルリン・フィルの団員たちは、「マエストロが!信じられない!今までだって一度だってこんな事はなかった。」と口々に驚きの声を挙げたと言う。カラヤンの特別控室に案内された彼女は、「あなたをお迎えにあがりした。」と挨拶すると、カラヤンは笑顔で、「何を演奏しますか?」と尋ねたという。その時、私たちが練習していたのは、ベ−ト−ベンの第9交響曲「合唱」と序曲「エグモント」であった。
12時をまわる頃、カラヤンは、にこやかに車に乗り込み私たちの待つ上智大学のある四ツ谷に向かった。
一方、カラヤンが来るのを朝から待っている私たち部員約80名は、まだ半信半疑である。「本当に来るのかなぁ」みんな、そんな気持ちであった。カラヤンの気を悪くすることのないように私たちは、演奏会用の黒の上下のス−ツに着替えていた。また、カラヤンに万一の事があってはならないという配慮から、大学内外は、物々しい警備体制が秘密裏にひかれた。
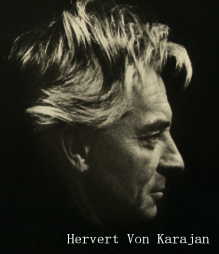 年も明けた1974年1月14日(月)第17回定期演奏会を迎えた。カラヤンが振ったオケということで聴衆の入りはすごかった。上野の東京文化会館大ホールは立ち見客が出るほどであった。ベートーベン序曲《エグモント》、交響曲第9番《合唱》。大成功であった。さっそく、その演奏会のテープをカラヤンに送った。カラヤンからは称賛の手紙が送られてきた。
定演も終わり、いよいよ、ベルリン行きの本格的な練習が始まった。曲は、ウエ−バ−歌劇「魔弾の射手」序曲(コンク−ル課題曲)、武満徹「弦楽のためのレクイエム」、ブラ−ムス交響曲第4番である。
春休み、みなアルバイトに燃えていた。3月下旬、千葉県岩井にて1週間の合宿。しかし練習は思うようにはかどらない。数人の4年生が卒業したために演奏レベルが低下してしまったのである。
4月に入り、40人余りの新入生が入部してきたが、例外を除いてはドイツ公演には連れていけないことになっていた。4月下旬、正式な招待状が送られてきた。
新たな障害である。予想以上に自己負担がかかりそうである。ドイツ滞在費はカラヤン財団持ちであるが、旅費は全額自己負担であるということが明らかになった。約20万円、当時としては大金である。経済的困難な人のために銀行ロ−ンの制度が取り入れられた。ベルリンでのコンク−ルの日程も決まり、それに先立つボンでの演奏会も決定した。
6月に入り、例年通り、東京での定期演奏会が開かれた。この演奏会は、ドイツでの成果を占うものであったが大失敗であった。技術的にも精神的にも未熟で表面的でしかない演奏であった。外部から、しきりに批判の声が聞こえた。「あれで、ドイツだって。」
ドイツ演奏旅行であって、ドイツ観光旅行ではない。ドイツは、バッハ、ベ−ト−ベン、ブラ−ムス等多くの作曲を生み出している音楽の都である。ドイツの人々は音楽を通して、私たちを見るのであり、私たちは日本の代表なのである。
東京での定演の反省として、東京芸大を始め他大学より10名程の優秀な演奏者の補充が決まった。練習もこれまでとは違った気迫と緊張感がみなぎりはじめた。演奏が向上すれば、合奏する歓びも増すものである。充実感を感じながら、演奏は加速度的に高まっていった。
ドイツ出発1週間前、総仕上げの合宿が私の地元、群馬県の富岡市の貫前神社近くの社会教育館で行われた。神社で手を合わせる皆の気持ちは同じであった。
「ドイツ公演が、うまくいきますように。」 (Sophia Philharmony:Horn mkudos910@yahoo.co.jp 改訂98/12/10)
東京新聞記事より
朝日新聞記事より
ドイツ演奏旅行
(参考文献)
チャンスをつかむためには積極的な行動を
(江川ひろし「3分間の名スピーチ」より)
昭和48年の秋のこと、日本にヘルベルト.フォン.カラヤンさんが来日したとき、すばらしい逸話が生まれました。それはカラヤンさんが学生のアマチュア楽団のために、みずから指揮棒を振ったという話です。
カラヤンさんは世界第一級の指揮者です。また、この天才音楽家は気むずかしいことで知られており、関係者は大変な神経の使い方だという報道も新聞をにぎわしていました。
ところでここに、新聞には報道されずNHKのテレビだけに流されたひとつのニュースがありました。それが冒頭に述べた素人管弦楽団の指揮という美談です。
それには次のようなひとりの女子学生の積極的な行動がありました。彼女はテレビに映るカラヤンの表情を見て、なんと人間的深味をたたえた顔だろう、この人はきっと心のやさしい人にちがいない。私たち素人の管弦楽団を指揮してくださらないものだろうか、お願いしてみよう、と思いたったのです。そしてドイツにはよい果物が少ないそうだからと蜜柑を一籠もって訪ねました。
はじめに、マネージャーと面会して手順を考えていました。するとなんと思いがけなく廊下の向こうからカラヤンさん、その人がくるではありませんか。彼女は思い切って積極的に声をかけ、あいさつしました。
「日本ではあなたのことを神さまのように思っています。とても私たちアマチュア楽団などの指揮なんかしていただけないと思いますが、もしその夢がかなえられるなら、と思ってお願いにまいりました。」
彼女はドイツ語を習っていたので、これだけの言葉を一生懸命覚えて行ったのだそうです。そして・・。
テレビのニュースは、学生たちの楽団を前に、あの瞑想スタイルで、しなやかに指揮をする神秘的なカラヤンの姿を映しました。
カラヤンさんは、「私は神さまなんかじゃありませんよ。若い人のアマチュア楽団の指揮をしないなんてことはありません」とやさしく語ったということです。
気むずかしくて有名な世界最高峰の指揮者と素人楽団のとり合わせ、この奇跡のような出来事をあなたはどう思いますか。
話を交わすことで、人と人とのむすびつきができるのです。言葉を交わすことで人間関係が生まれるのです。もし彼女がカラヤンさんと廊下で会ったときに、「あとにしよう」と声をかけなかったら、このすばらしいエピソードは生まれなかったでしょう。
人との出会いを大切に。そしてチャンスを逃がさずに。チャンスの神さまが通ったら、積極的に声をかけて、勇気を持って前髪をつかみましょう。チャンスの神さまは後ろが禿げています。
年も明けた1974年1月14日(月)第17回定期演奏会を迎えた。カラヤンが振ったオケということで聴衆の入りはすごかった。上野の東京文化会館大ホールは立ち見客が出るほどであった。ベートーベン序曲《エグモント》、交響曲第9番《合唱》。大成功であった。さっそく、その演奏会のテープをカラヤンに送った。カラヤンからは称賛の手紙が送られてきた。
定演も終わり、いよいよ、ベルリン行きの本格的な練習が始まった。曲は、ウエ−バ−歌劇「魔弾の射手」序曲(コンク−ル課題曲)、武満徹「弦楽のためのレクイエム」、ブラ−ムス交響曲第4番である。
春休み、みなアルバイトに燃えていた。3月下旬、千葉県岩井にて1週間の合宿。しかし練習は思うようにはかどらない。数人の4年生が卒業したために演奏レベルが低下してしまったのである。
4月に入り、40人余りの新入生が入部してきたが、例外を除いてはドイツ公演には連れていけないことになっていた。4月下旬、正式な招待状が送られてきた。
新たな障害である。予想以上に自己負担がかかりそうである。ドイツ滞在費はカラヤン財団持ちであるが、旅費は全額自己負担であるということが明らかになった。約20万円、当時としては大金である。経済的困難な人のために銀行ロ−ンの制度が取り入れられた。ベルリンでのコンク−ルの日程も決まり、それに先立つボンでの演奏会も決定した。
6月に入り、例年通り、東京での定期演奏会が開かれた。この演奏会は、ドイツでの成果を占うものであったが大失敗であった。技術的にも精神的にも未熟で表面的でしかない演奏であった。外部から、しきりに批判の声が聞こえた。「あれで、ドイツだって。」
ドイツ演奏旅行であって、ドイツ観光旅行ではない。ドイツは、バッハ、ベ−ト−ベン、ブラ−ムス等多くの作曲を生み出している音楽の都である。ドイツの人々は音楽を通して、私たちを見るのであり、私たちは日本の代表なのである。
東京での定演の反省として、東京芸大を始め他大学より10名程の優秀な演奏者の補充が決まった。練習もこれまでとは違った気迫と緊張感がみなぎりはじめた。演奏が向上すれば、合奏する歓びも増すものである。充実感を感じながら、演奏は加速度的に高まっていった。
ドイツ出発1週間前、総仕上げの合宿が私の地元、群馬県の富岡市の貫前神社近くの社会教育館で行われた。神社で手を合わせる皆の気持ちは同じであった。
「ドイツ公演が、うまくいきますように。」 (Sophia Philharmony:Horn mkudos910@yahoo.co.jp 改訂98/12/10)
東京新聞記事より
朝日新聞記事より
ドイツ演奏旅行
(参考文献)
チャンスをつかむためには積極的な行動を
(江川ひろし「3分間の名スピーチ」より)
昭和48年の秋のこと、日本にヘルベルト.フォン.カラヤンさんが来日したとき、すばらしい逸話が生まれました。それはカラヤンさんが学生のアマチュア楽団のために、みずから指揮棒を振ったという話です。
カラヤンさんは世界第一級の指揮者です。また、この天才音楽家は気むずかしいことで知られており、関係者は大変な神経の使い方だという報道も新聞をにぎわしていました。
ところでここに、新聞には報道されずNHKのテレビだけに流されたひとつのニュースがありました。それが冒頭に述べた素人管弦楽団の指揮という美談です。
それには次のようなひとりの女子学生の積極的な行動がありました。彼女はテレビに映るカラヤンの表情を見て、なんと人間的深味をたたえた顔だろう、この人はきっと心のやさしい人にちがいない。私たち素人の管弦楽団を指揮してくださらないものだろうか、お願いしてみよう、と思いたったのです。そしてドイツにはよい果物が少ないそうだからと蜜柑を一籠もって訪ねました。
はじめに、マネージャーと面会して手順を考えていました。するとなんと思いがけなく廊下の向こうからカラヤンさん、その人がくるではありませんか。彼女は思い切って積極的に声をかけ、あいさつしました。
「日本ではあなたのことを神さまのように思っています。とても私たちアマチュア楽団などの指揮なんかしていただけないと思いますが、もしその夢がかなえられるなら、と思ってお願いにまいりました。」
彼女はドイツ語を習っていたので、これだけの言葉を一生懸命覚えて行ったのだそうです。そして・・。
テレビのニュースは、学生たちの楽団を前に、あの瞑想スタイルで、しなやかに指揮をする神秘的なカラヤンの姿を映しました。
カラヤンさんは、「私は神さまなんかじゃありませんよ。若い人のアマチュア楽団の指揮をしないなんてことはありません」とやさしく語ったということです。
気むずかしくて有名な世界最高峰の指揮者と素人楽団のとり合わせ、この奇跡のような出来事をあなたはどう思いますか。
話を交わすことで、人と人とのむすびつきができるのです。言葉を交わすことで人間関係が生まれるのです。もし彼女がカラヤンさんと廊下で会ったときに、「あとにしよう」と声をかけなかったら、このすばらしいエピソードは生まれなかったでしょう。
人との出会いを大切に。そしてチャンスを逃がさずに。チャンスの神さまが通ったら、積極的に声をかけて、勇気を持って前髪をつかみましょう。チャンスの神さまは後ろが禿げています。